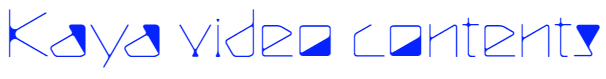【Kaya ONLINE SHOP】
明日の教室DVD・audioシリーズ、SOYA DVDシリーズ、Kaya DVDシリーズ、野口芳宏DVDシリーズ
の販売(DL版)サイトです
★ABOUTの【注意点】を必ずお読みください★
スマートフォンなど、携帯端末とBASEのアプリから購入できません パソコンからの購入が前提となります
メールマガジンを受け取る
-

(2割引)明日の教室シリーズ第53弾「『授業』がすべて」木幡 寛 フリースクールジャパンフレネ代表
¥2,640
(2割引キャンペーン中) 「『授業』がすべて」 木幡 寛 フリースクールジャパンフレネ代表 2017年4月15日 於:京都橘大学 ※講師の所属、肩書等は制作当時のものです (◆最新DVD情報は含まれません) ⚫写真のDLは不可です 第1部 Why?を追及する―『体積』とは何か?そして、密度へ・・・。 92分 第2部 学校知を疑え!―『モーメント』から見る学校知の限界 22分 第3部 『異分母分数の加減』でアクティブラーニング―枠ではなく教材 30分 第4部 質疑応答 23分 【メッセージ】文科省のお墨付きでアクティブラーニングが学校現場で話題になり、早速あちこちで実践の模索が始まっています。しかし、戦後民間教育に関わってきた多数の教師に言わせれば、何をいまさらといった感もなくはないでしょう。 そう、今から50年以上前から志を持つ教師は、子ども自らに考えさせ、そこから教師も学んで行くという体験をしていたのです。与えられたものをアレンジするのではなく、教材を教科書以外に求めてきた多数の教師は、「授業は楽しいだけでいい」と断言します。 授業を『楽しい&わかる』で分類すると、次のようになるでしょう。 A たのしくてわかる授業 B 楽しいけれどわからない授業 C つまらないけれどわかる授業 D つまらなくてわからない授業 学校の授業は、大半、CかDであり、多くの教師はAを目指すでしょう。しかし、私は子どもと共にB『楽しいけれどわからない授業』を追及していきたいと思います。ワクワクしながら一つの疑問を追及し、「ああ、私はきっとこういうことを知りたかったのだ」という未来完了形的な授業・・・。そこのベースにあるのは、教材です。教材が思考のすべてを支配すると言っても過言ではありません。学ぶ以前のシンキングは、教材が90%以上の重要性を持ちます。 アクティブの強調は、教材をないがしろにし枠にこだわる、ある意味危険な考えでもあることを忘れてはいけません。教材をベースに至極まともな授業をどう作っていくか・・。このDVDでそのことが少しでも伝われば授業屋冥利に尽きます。 【木幡 寛(こはたひろし)プロフィール】1949年北海道北見市生まれ。青山学院大学文学部教育学科を卒業後、埼玉県公立小学校、東京都三鷹市明星学園に勤務。1985年自由の森学園の創設に関わる。1984年ベルギーのルーバン大学で開催されたフレネ教育者国際集会に故村田栄一氏(教育評論家)、里見実氏(國學院大學名誉教授)と共に日本人初の正式参加。戦後民間教育の教育実践を発表。以来、フロリアナポリス(ブラジル)、ヘマーバン(スェーデン)、クラクフ(ポーランド)の国際集会で世界各国のフレネ教育者に算数の授業を提案。 1996年より1998年まで自由の森学園高等学校校長。1998年 自由の森学園を会場にフレネ教育者国際集会。1999年 自由の森学園を退職し、フリースクールジャパンフレネ設立。以来、オルタナティブ教育に関わる。1977年より現在に至るまで、北は北海道から南は九州沖縄まで全国各地で公開授業・講演を行う。また、雑誌インタビューやテレビ番組などにも多数出演。数学教育協議会常任幹事、教育誌「ひと」編集委員としても活動する。教育考古学会主宰。 【主著・共著】 ★カレーを作れる子は算数もできる(講談社現代新書)★考える力がグングン育つ「なぜ?なに?」ふしぎ遊び35(PHP研究所)★「学ぶ力」がグングン育つ学習法(PHP研究所)★算数のできる子どもを育てる(講談社現代新書)★秋山仁先生の楽しい算数教室(全10巻ポプラ社) ★はてなし世界の入り口(共 福音館) 授業がすべて(共 太郎次郎社) 他多数 #明日の教室 #木幡寛 #フリースクール #ジャパンフレネ #授業 #体積 #算数 #理科 #学校知 #生活知 #モーメント #異分母分数の加減 #アクティブ・ラーニング #京都橘大学 #教育 #糸井登 #池田修 #平井良信 #有限会社カヤ #kaya #DVD #DVDシリーズ

-

(4割引)明日の教室シリーズ第05弾「コミュニケーションティーチングによる地域力再生事業 演劇発表公演+シンポジウム」
¥1,980
(4割引キャンペーン中) コミュニケーションティーチングによる地域力再生事業 演劇発表公演+シンポジウム 宇治市立菟道第二小学校3年生児童+劇団衛星 池田 修、糸井登、蓮行、北川達夫、平田オリザ 平成21年11月3日 於:宇治茶会館 ※講師の所属、肩書等は制作当時のものです ⚫写真のDLは不可です 【画角4:3】 第1部 演劇発表公演(47分) 「チョイチョイ星人がやってきた!in 宇治」 宇治市立菟道第二小学校3年生児童+劇団衛星 コミュニケーションティーチングとは、演劇の手法を応用した教育プログラムのことです。子どもたちは、単に演劇を作るだけでなく、コミュニケーション能力を高めていくことができるようになっています。今回は、宇治をテーマに、コミュニケーションティーチングを用いて、子どもたちがプロの俳優と共に5回のワークショップを経て作りあげたものを上演しました。 第2部 シンポジウム(1時間30分) 平田オリザ 劇作家・演出家 大阪大学コミュニケーションデザインセンター教授 北川達夫 フィンランド教材作家 日本教育大学院大学客員教授 池田 修 京都橘大学准教授 糸井 登 京都府宇治市立菟道第二小学校教諭 蓮 行 劇団衛星 カナダやオーストラリア、フィンランドでは学校教育に演劇が取り上げられ、大きな役割を果たしています。日本でも、演劇を授業に活かす試みが広がりつつあります。 シンポジウムでは、コミュニケーションティーチングの提唱者である平田オリザ氏、フィンランド教材作家の北川達夫氏、京都橘大学准教授の池田修氏、また、実際に現場でプログラムを作ってきた小学校教諭の糸井登氏と劇団衛星の蓮行氏が登壇。コミュニケーションティーチングの基本的な情報や学校現場でのエピソード、海外の事例などを交えて、その必要性と魅力を語り合いました。

-

(3割引)明日の教室シリーズ第58弾「写真でテキストを読解する、学級づくりで大切なことってなんだろう?」池田修、糸井登
¥2,310
(3割引キャンペーン中) 写真でテキストを読解する~主体的・対話的で深い学びは、作って学ぶ~ (101分 池田 修 京都橘大学教授、明日の教室代表 学級づくりで大切なことってなんだろう? (61分) 糸井 登 立命館小学校教諭、明日の教室代表 2018年4月21日 於:京都橘大学 ※講師の所属、肩書等は制作当時のものです ⚫写真のDLは不可です 【池田修氏メッセージ】 子供達の周りには、画像・動画情報があふれています。Lineのスタンプ、Snowの写真、Tic Tocの動画などなど。しかし、子供達にその取り扱いについて学習する機会は非常に少ないのが現状ではないでしょうか。 今回の、ことわざを画像化するというワークショップは、画像情報を作ることを通して、文字情報を理解しようという試みです。文字情報を正確に読みとらなければ、画像情報に変換することはできません。このことを通して、画像・動画情報にはどのような特性があるのかを考えるデザインになっています。 また、新しい学習指導要領が求めているコンテンツからコンピテンシーへ学習観の変換や、深い学びに対応する「作って学ぶ」についても資料をもとに説明をしています。これからの授業づくりへのヒントがたくさん得られるものと思っております。 【プロフィール】 京都橘大学 発達教育学部児童教育学科 教授 「国語科を実技教科にしたい、学級を楽しくしたい」をキーワードに研究。 恐怖を刺激する学習ではなく、子どもの興味を刺激する学びに着目している。学習ゲームにも詳しい。専門は、国語教育学、学級担任論、特別活動論。 特に学級担任の仕事を教える学級担任論は、全国の教員養成大学で最初に開講され、いまでも殆ど唯一の授業である。最近は、漢字学習材開発、甲骨文字の再現、ことわざの画像化、思考コード研究、作って学ぶなどに力を注いでいる。趣味は料理、写真、ハンモック。 教育研究会 明日の教室 主催、ブログ「国語科 学級経営のページ blog」 ●主な著書 単著『中等教育におけるディベートの研究』(大学図書出版)『こんな時どう言い返す』(学事出版)『新版 教師になるということ』(学陽書房)。『スペシャリスト直伝! 中学校国語科授業成功の極意』(明治図書) また、 電子ブックで『5分、5ステップではじめる料理 ~ 包丁を持ってみようかなあと思い始めているあなたへ ~』 【糸井登氏メッセージ】最近、学級づくりを「織物」に例えた、「織物は縦糸と横糸からできている」という話が広がってきています。「縦糸」と「横糸」の二つがないと布にはならないという話です。私は「縦糸」をルール、「横糸」を子どもたち同士のつながりと解釈しています。教師は学級がうまくいっていないなと感じた時、どうしても「縦糸」の強化に向かいがちです。そして、多くの教師が、説教を始めてしまうのです。しかし、「織物」を意識するならば、「ああ、もっと子どもたちのつながりを深める活動が必要だなあ」と考えなければならないのではないでしょうか。この講座では、子どもたちがつながりを意識するようになるいくつかの活動を紹介しました。先生方の学級づくりの参考になれば幸いです。 【プロフィール】 1959年生まれ。京都府の公立小学校に27年間勤務した後、2010年から立命館小学校に籍を移す。「明日の教室」代表。「NPO法人・子どもとアーティストの出会い」理事。主な著書に「糸井登 エピソードで語る教師力の極意」(明治図書)、編著に「言語活動が充実するおもしろ授業デザイン集低・中・高学年」(学事出版)「明日の教室発!子どもの力を引き出す魔法の学級経営」(学事出版)などがある。 #明日の教室 #池田修 #DVDシリーズ #58弾 #糸井登 #小学校 #中学校 #教諭 #授業づくり #学級づくり #教育 #共同学習 #アクティブラーニング #アクティビティ #作って学ぶ #京都橘大学 #立命館小学校 #板書 #平井良信 #有限会社カヤ #kaya #縦糸 #横糸 #有限会社カヤ #kaya #DVD #DVDシリーズ

-

(2割引)明日の教室シリーズ第37弾「『ICT活用』はどこに向かうか」堀田龍也 東北大学大学院情報科学研究科 教授
¥2,640
(2割引キャンペーン中) 「ICT活用」はどこに向かうか 堀田龍也 東北大学大学院情報科学研究科 教授 2014年4月26日 於:京都橘大学 ※講師の所属、肩書等は制作当時のものです ⚫写真はDL不可です 1.自己紹介 5分 2.【確認】ICT活用の本質 9分 3.なぜ今,実物投影機か 37分 4.教科書を見直す 48分 5これからのICT活用 29分 6.歩み始める人を支援したい 15分 7.質疑応答 16分 今や普通教室にICTが導入されていること自体は珍しいことではありません。しかし中には,授業にとってあまり役立ちそうにないICTや,機能が多すぎてなかなか使いにくいICTを導入してしまっている例もあります。教師は良い授業をしたいのですから,このようなICTを敬遠する傾向にありますが,すると「ICTも使えない教師は問題だ」というような風潮で取り上げられたりします。 「学校現場のICT導入は,授業の本質を見逃してしまっているのではないか」これが私の問題意識です。 今回の講演では,ICTの例として実物投影機を取り上げ,映される教科書をどう読解するのかという点について掘り下げ,教師が持つべきICT活用指導力について考えて いきます。 1964年,熊本県天草県生まれ。 東京学芸大学卒業後,東京都の小学校に5年間勤務。その後大学に転身し,富山大学教育学部,静岡大学情報学部等を経て,メディア教育開発センター勤務時に文部科学省を併任。玉川大学教職大学院を経て,2014年4月より東北大学大学院情報科学研究科・教授。日本教育工学協会(JAET)会長,日本教育工学会理事などを歴任。中央教育審議会初等中等教育部会道徳教育専門部会委員,文部科学省「情報活用能力調査に関する協力者会議」委員,「ICTを活用した教育の推進に関する懇談会」委員など教育情報化政策に多く関わる。 代表的な著作 ・高橋純・堀田龍也 編著(2009):『すべての子どもがわかる授業づくり -教室でICTを使おう』,高陵社書店 ・堀田龍也・野中陽一 編著(2008),『わかる・できる授業のための教室のICT環境』,三省堂 ・堀田龍也 著(2004):『メディアとのつきあい方学習』,ジャストシステム #明日の教室 #堀田龍也 #ICT #ICT活用 #東北大学大学院情報科学研究科 #教授 #本質 #実物投影機 #教科書 #見直すこれからのICT活用 #歩み始める人 #支援 #質疑応答 #普通教室 #学校現場のICT導入 #授業の本質 #問題意識 #講演 #ICTの例 #教師 #ICT活用指導力 #教育 #京都橘大学 #糸井登 #池田修 #平井良信 #有限会社カヤ #kaya #DVD #DVDシリーズ

-

(3割引)明日の教室シリーズ第33弾「子どもが育つ授業&学級づくり」伊藤邦人、正頭英和 立命館小学校教諭
¥2,310
(3割引キャンペーン中) 「子どもが育つ授業&学級づくり」 伊藤邦人 立命館小学校教諭 正頭英和 立命館小学校教諭 2013年12月14日 於:京都橘大学 ※講師の所属、肩書等は制作当時のものです http://sogogakushu.gr.jp/asunokyoshitsu/dvd_033.htm https://youtu.be/KPp-79twE8k ⚫写真はDL不可です 第1部 「マニュアル授業からクリエイティブ授業への転換の仕方」(67分) 伊藤邦人立命館小学校教諭 これまで、さまざまな授業を見たり、したりしてきました。その中で、子どもたちが主体的に生き生きと学んでいる授業もあれば、子どもたちが受動的になって空気が沈んでしまう授業もあります。では、どうすれば、常に子どもたちが主体的に学ぶ授業をつくることができるのか。私は、教材を料理する「仕掛け」が不可欠だと考えます。今回は、具体的な授業や演習に即して、さまざまな仕掛けを紹介していきます。 伊藤邦人先生(いとうくにと)/立命館小学校教諭 1980年生まれ。 学習塾勤務を経て,現在立命館小学校教諭。 「クリエイティブ」を教育の柱とし,子どもを最大限伸ばす学級経営・授業づくりの研究を進めている。「マニュアル授業から脱却する! 算数のクリエイティブ授業 7の仕掛け・30の演出」(明治図書)他 第2部 心を育てる学級経営 (68分) 正頭英和 立命館小学校教諭 「子どもたちに必要なのは正解ではなく、納得解である。」私たちは子どもたちに正解を伝える努力はしていても、納得させる努力は不足しているのではないでしょうか。特に学級経営という分野においては、不足しているような気がします。本講座では「体感」ということをベースに、子どもたちに納得させる方法を具体的にご紹介させていただきます。また、それらの活動をどのように年間計画に配置するか、どのように計画的に子どもの心を育てるのか、そのポイントと実践例をご紹介させていただきます。 正頭英和先生(しょうとう ひでかず)/立命館小学校教諭 1983年生まれ。 立命館中学校高等学校勤務を経て、現在立命館小学校教諭。 英語専科として小学校に赴任し、現在6年生を担任している。「厳しさ・楽しさ・やさしさ」が融合された教師を目指して、日々の教育活動に奮闘している。 #明日の教室 #伊藤邦人 #正頭英和 #子どもが育つ授業&学級づくり #立命館小学校教諭 #マニュアル授業 #クリエイティブ授業 #転換 #仕掛け #授業 #演習 #学習塾勤務 #クリエイティブ #学級経営 #授業づくり #マニュアル授業から脱却する #算数のクリエイティブ授業 #7の仕掛け #30の演出 #心を育てる学級経営 #正解 #納得解 #体感 #年間計画 #実践例 #英語専科 #厳しさ・楽しさ・やさしさ 教育活動 #教育 #京都橘大学 #糸井登 #池田修 #平井良信 #有限会社カヤ #kaya #DVD #DVDシリーズ

-

(3割引)明日の教室シリーズ第16弾「ファシリテーション・グラフィック入門」藤原友和 函館市立昭和小学校教諭
¥2,310
(3割引キャンペーン中) ファシリテーション・グラフィック入門 藤原友和 函館市立昭和小学校教諭 ※講師の所属、肩書等は制作当時のものです 平成23年6月11日 於:大阪市立弁天町市民学習センター 【画角4:3】 Opening (12分) 初めて会った参加者同士でグループをつくる。「バースデーライン」のアクティビティをアレンジしたアイスブレイキングを行い,4人グループに分かれた後はA4の紙を名刺代わりに使って自己紹介をした。 第1部 What's FG ? (56分) 「ファシリテーション」及び「ファシリテーション・グラフィック」について簡単な定義を行い,実践例を紹介した。理科の授業でのFG,校内研修において職員全員で取り組んだFG,授業参観で保護者も参加したFG,研究大会に向けて市の研究サークルで取り組んだFG,民間の研究団体で講師の話を記録したFGなど豊富な具体例で説明。さらに「模擬会議」でライブFGを披露した。 第2部 How-to FG ? (37分) FGの仕事はごく簡単に言うと「何を拾うか」と「どこに描くか」の二通りしかない。それらを円滑に進めていくためのレイアウト(「マンダラ型」と「議事録型」)や議論の進み方(「タテの議論とヨコの議論」),図解スキル(樹形図/ベン図/点グラフ),色についての基本的な知識を紹介。4人グループで実際にFGを体験しながらワークショップを行った。 第3部 Why, FG ? (30分) なぜ学校の現場にFGが必要なのか,「明日の教室 大阪分校」主催者の川本敦氏によるインタビュー。FG導入までの経緯や,進めていく上での注意点など,講座では紹介しきれなかったエピソードが満載。